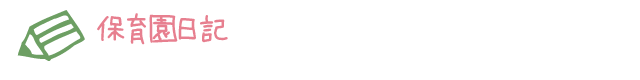オズレストラン
[平成27年2月21日]
木金の2日間、保育園はお店屋さんでした。
おもちゃ屋さん、絵本屋さん、ゲームコーナーなど、各クラスが色んなお店になっています。
切り倒した丸太で年長が作った木のパズル。3歳のおもちゃ屋さんで、素敵な商品になって並んでます。
年長は「オズレストラン」。おしゃれなバーガーショップです。
受付のノボリにドロシーとカカシのイラスト。
お衣装もドロシー&カカシ。
よく働きます。「お皿を下げてよろしいですか?」
ハンバーガーではなく、ハム・バーガー!笑
「わ、すごい、二段ベッド!」
……、確かに。ちなみにこちらは大人用。お子様は一段ベッドです。
大繁盛!
4月の頃から年長クラスでずっと聞き続けてきたお話「オズの魔法使い」。今回のお店屋さんごっこでは、みんなで壁面を仕上げ、衣装を整えて、素敵なレストランになりました。
森のサッカーボール
[平成27年2月20日]
冬の林。常緑樹が多いので緑色&日蔭の割合が多めです。今後少しずつ落葉樹の割合を増やしていきたいと思っています。寒いですが、子ども達はよく遊びます。
1歳児クラスの遊びはとにかく木の実拾い。拾ったものを盛んに見せにきます。「見て、どんぐりあった。」「園長先生、サッカーボール。」
サッカーボール……………?
正体はこちらです。ヒノキの実。子ども達は「森のサッカーボール」と呼んでいます。模様がサッカーボールに似ていませんか? 直径1センチにも満たない小さな実ですが、どんぐり同様大人気。
木の実拾いの合間に丸太でドラミング。色んな音を楽しみます。
枝拾いも盛ん。大きくて長い枝を発見して大得意。
年長さんと一緒に葉っぱの冠作り。
こんな感じのやつです。
1歳さんも林が大好き。日射しが少し温かく、風も無く、今日はとても気持ちのよい林でした!
おねはん
[平成27年2月17日]
2月15日はお釈迦さまのお亡くなりになられた日で、その日を涅槃会(ねはんえ)と呼びます。
涅槃とは、昔のインドの言葉「ニルバーナ」「ニッバン」が音写されたもので、「火を消す」というような意味の言葉です。煩悩の炎を吹き消したスーッと静かな状態を指します。それはつまり「さとり」のことなのですが、ではなぜこれがお釈迦様のご入滅(死)を表す言葉として使われるのでしょうか。
人はどんなに修行をしても肉体があることで様々に心を惑わされる可能性があります。熱い寒いを感じたり、目に見えるもの、口で味わうものなどにいちいち心を揺らされてしまうのです。でも死んで肉体が無くなれば、そうした感覚もすべて無くなり、いよいよ本当に静かな境地を獲得することができる、と考えたのです。死 → 肉体の消滅 → 感覚の消滅 → 本当のさとり、というわけです。このようなことから、涅槃がお釈迦様のご入滅を表す言葉として使われているのです。
ちなみに、さとりを得るということは「仏に成る」ということですが、私達が死後に「成仏」を願うのも同じことです。死ぬことで肉体が滅し、あらゆる迷いが無くなり、静かな安らかな境地を獲得できますように、と願うわけです。安らかな世界の獲得は、いつも色々なことに悩み苦しみながら生きている私達人間の根本的な願いなのでしょう。
園では13日に子ども達と本堂にあがり、大きな涅槃図を見てお釈迦様に思いを馳せました。お釈迦さまのお亡くなりの物語を聞き、みんなでお焼香をして、六つの約束をお唱えしました。人間としてのお釈迦様は遠い昔に亡くなられましたが、お釈迦様がお説きになった教えは時を超えて受け継がれ、子ども達の心の中に生き続けていきます。
六つの約束(六波羅蜜)
一つ、お友達と仲良くできる子になりましょう。(布施)
一つ、お父様お母様の言いつけをよく守れる子になりましょう。(持戒)
一つ、がまん強くしまいまでやり遂げる子になりましょう。(忍辱)
一つ、丈夫な体でよい子になりましょう。(精進)
一つ、慌てないでいつも心の優しい子になりましょう。(禅定)
一つ、物事をよく考えて良いことをする子になりましょう。(智慧)
大きな氷が取れました。
バレンタイン
[平成27年2月13日]
何やら熱心に作業中
できました。
バレンタインのチョコだそうです。
いいな♪
ままごとは、子ども達の素晴らしい仕事です。