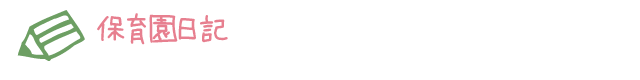お泊まり保育
[令和1年9月13日]
先週の金曜土曜の二日間、年長児のお泊まり保育を行いました。遅くなりましたが、少し報告です。
夏の間ほとんど出入りしなかった林。久しぶりにここで存分に遊ぶ計画です。
虫かごや図鑑が色々並べられて、楽しい1日のスタートです。
久しぶりの林で待ちきれない様子の子供達。
草地では早速虫取り合戦が始まりました!
捕まえては図鑑で調べ、友達とあれこれ議論しています。
虫かごの中を覗くとオンブバッタが大豊作。立派なトカゲ(ニホンカナヘビ)もいます。
「さっきね、虹色のトカゲがいたんだよ。捕まえられなかった…。」と、悔しそうに呟きながらぶらつく男子。
虹色のトカゲというのは「ニホントカゲ」のことだと思います。メタリックで虹色に輝くニホントカゲと、茶色くカサカサしたボディのニホンカナヘビ(上の写真)。敷地内はこの2種類がほぼ均等な割合で生息している感じです。どちらも子供達にとって素晴らしい遊び相手。この他にチョウや大きなカマキリなどもゲッツ。
こちらの女子連は花びらや木の葉をすり潰して色水作りに夢中。
この日の朝にちょうど満開のように咲いた朝顔の花びらを摘んで、色水の材料にしていました。
すごくきれいな紫の色水が完成。
陽の光に透かしながら「ほら見て、すごいきれいだね!」と。
幸せそうです。
こんな色もできています。
私の提案で、近くに生えていた山椒の葉や実も投入。「あ!いい匂いする!!」「ホントだ!!」と好反応。(^^) 色+匂いで五感の刺激をパワーアップしちゃいます。
こちらは木工作コーナー
みんな夢中で制作に打ち込んでいます
試行錯誤しながら木を選び、サイズを確かめながら仮組みします。
だんだん出来上がってきましたよ。
ついに完成! \(^o^)/
ままごともじっくりと展開。
夜になりました。先日来集めていた薪を組んでキャンプファイヤです。子供達が一人一人順番に薪を投入していきます。
燃え上がる炎を眺めながらトーク&シング。用意していた歌の他に、子供達が自然に口ずさみ始めた歌「パプリカ」も、みんなで一緒に歌って踊りました。
・・・・・・・・・・・・・・・
翌日のお帰りの直前、この二日間の活動のシェアリング。
今回私がバタバタしていてなかなか写真を撮れなかったので、日記の掲載はこの辺で終了です。でもこの二日間を通じて子供たちは様々な体験をしました。林での遊び、夕食作り、デザートのアイス作り、キャンプファイヤー、テラスでの露天風呂、大きなテントでみんな一緒の宿泊、鬼子母神堂での朝のお勤め、この夏最後のプール遊びなどなど…。
みんなよく遊び、よく眠り、充実の二日間を過ごすことができました。
・・・・・・・・・・・・・・・
後日改めて年長の部屋を覗いてみると……
こんな動物が
首にリードをつけて飼われていました。妙に愛くるしい顔です。笑
クジラもリード…
こんなカッコいいやつにも、よく見たらリードが…!(左端)
子供たちの遊びの物語は、日々刻々と変化しながら続いていくのです。
楽しいなー!
台風の贈り物
[令和1年9月9日]
今回の台風で、恐らくほぼ全ての栗が落ちました。
園で初めて収穫する栗。なかなか立派です。お味はどうか…。今年は収穫量が少ないですが、恐らく来年からはグッと増えるでしょう。楽しみです!
砂場の脇には大量のぎんなんが…。こちらはまだちょっと未熟かな?
お寺の木はだいぶ折れました。広大な敷地の全域がほぼこのような状態。近隣の道路も含め、片付けに数日かかりそうです。しかも追い討ちをかけるような今年一番級の猛暑…。涙)
妙福寺は大木に囲まれているので、ある意味台風が一番怖いです。今回はお堂などの建物や境内の構造物に被害がなく、近隣住宅の損壊などもありませんでした。よかった〜。
良きにつけ悪しきにつけ、これらはみんな台風の贈り物。台風の後にいつも思うのは、片付けも含めて、この贈り物を子供達と一緒に遊び尽くしたい!ということ。でも、住職として色々な対応に追われそれどころではないのが辛いところです。
がんばろー!
薪集め
[令和1年9月3日]
今日は月2回の体操指導の日だったのですが、その合間を縫って数人の年長女子が担任と一緒に薪集めをしていました。今週末予定しているお泊まり保育の準備です。うちの園では猛暑を避けて秋口にお泊まりをするようにしています。毎日通っている園舎に皆で泊まって過ごす二日間は、子供達にとって最高に楽しい体験の一つです。
お泊まりの夜の楽しみの一つは、やはりキャンプファイヤでしょう。揺らめく炎を見つめたり、舞い上がる火の粉を追いかけたり。火を囲んで歌を歌い、友達と語り合い…、心も体も温まるようなひと時です。園庭でキャンプファイヤを出来るというだけでも幸せなことですが、さらに幸せなことに、子供たちはこの「妙福寺の森」で焚き火の材料集めから出来るのです。そんな保育園がどれほどあるでしょうか。
林をはじめとして敷地のいたるところで木の枝を集めることができるわけですが、今日は境内の一角にある貯木場(?)で良さそうな枝を物色していました。
かと思いきや…、
そこら中に溢れるセミの抜け殻に完全に心を奪われる女子連。笑
なぜかこれをやるわけです。
「園長先生、捕まえて!」というので捕まえました。少し小型のアブラゼミ。「あ、赤ちゃんゼミだね。(小さいから)」「羽がボロボロになってる…。」などと感想を述べ合って恐る恐るボディーにタッチ。地面に落ちてひっくり返っているやつを死んでると思って何気なく触ると、急に「ビービービービーッ!」って暴れてびっくりして「キャーッ!」ってなる。セミあるあるですね。だから恐る恐るです。(^^)
一通りセミで遊んで、肝心の枝の物色も終わって、
園庭に運びます。
さあ、これから体操指導。
あれ?体操の先生(右端)が真っ黒に日焼けしているじゃないですか…!焚き火で焼いたのかな?
肌の「黒さ」は七難隠す。高校の頃からの私の座右の銘。私は子供の頃から肌が透き通るように白くて、それが一種のコンプレックスでした。いやほんと、海とか川とかに行くと光って見えちゃうほど白いんです。涙)やっぱり男は黒くないと。高校・大学と水泳部で毎日外プールで泳いでいたわけですが、なぜか赤くなるばかりであまり黒くならない。だからもう、こういう真っ黒な肌は憧れ中の憧れです。ただ、色黒にも唯一難点があります。それはなんとなく着物が似合わないということ。真っ黒く日焼けしたお坊さんて、なぜかいかがわしい感じになっちゃうんですよね〜。気のせいかな…?おいおい、ここはインドかーい?!って。いーや日本、やっぱり色白のお坊さんの方がフィットする!そうやって自分を慰めながら日々頑張っております…。
よーし、みんなで焚き火を焚いてバーニーング・アップだ!!
引き取り訓練
[令和1年9月2日]
子供、職員、それぞれの楽しい夏休みがあっという間に終わり、9月になりました。二期のスタートです。本日は災害時引き取り訓練です。
午後4時、東京地方に大きな地震が発生。公共交通機関が全てストップし、保護者が職場から徒歩で子供を迎えに来るという設定です。園では地震の後に年長クラスから火災が発生。子供たちは全員園庭に避難しています。
お母さんのお迎え。職場から園までの徒歩での所要時間などを確認して引き渡し終了です。
この引き取り訓練は、年に一度のとても大切な訓練です。災害が発生した午後4時に職場を出発し、歩いて園まで迎えに来て欲しいわけですが、訓練なのでなかなか実際そこまではできないということもあると思います。でも、最低でも公共交通機関が完全に止まった場合を想定し、全行程徒歩でのお迎えのルートを確認していただきたいと思います。災害の状況によっては携帯電話の地図アプリ(Googleマップなど)も全く使えないということがあります。どの道をどちらの方角に向かって歩けば良いかを確認しておくだけでもかなり違うと思います。そして、いざという時はどうするか家族で話し合って欲しいです。こうした備えは、本当に「いざ」という場合の大きな助けになるはずです。
保護者の皆さま、ご協力ありがとうございました!