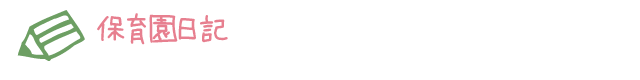おいなり山公園
[令和1年5月23日]
春の遠足です。
「今日これから行くところは『おいなり山公園』です。◯でしょうか、×でしょうか。」これは行きのバスの中で担任が出したクイズ。「違うよ!それじゃ食べ物になっちゃうよ!」と子供達は大笑い。
ということで、
今年の遠足は、稲荷山公園です!
エゴノキの白い花の絨毯
花の白にヘビイチゴの赤。映えます。
カバサーファー
キリンガールズ
それー!
見て、三角があった! と。
シロツメクサも
暖かな時間をくれます。
切り株のそばで何やら話し込んでいると思ったら、
ギョギョギョ〜!やっぱりシロアリ(成虫)の大群。こちらではまさに今日が旅立ちの日だったようです。
木陰で、
お弁当タイム。
だるまさんが
ころんだっ!
「これ面白い!」んだそうです。
見て、ここ歩けるよ! と。
ジオラマや
昔のお家にも興味津々。
年長の担任曰く「自分は最強の晴れ女」。へー!(^^) 確かに前日の土砂降りから打って変わって青空と白い雲。風もなく、暑くもなく寒くもなく最高の遠足日和になっちゃいました。手作りのフリスビー片手に広い原っぱで思い切り体を動かして遊び、探検バッグを肩から下げては草花や虫を夢中で採取。感性が豊か。のびのびいきいき。自然が大好きな妙福寺の子供達です。
よく考えてみると、なんだか普段とあまり変わらないような…?笑)
でも、これがいいんです!
グリーンピース
[令和1年5月17日]
良い天気。園庭に出ると日差しの暑さが真夏のようです…。
テラス前の花壇にはグリーンピース。
お!
えーと……、
あった!!
グリーンピースとサヤエンドウ!
こちらは園庭の一角にあるバンペイユの木。こないだの冬、ある事件が発生し子供達自身の手で収穫することができませんでした。
今年もたくさんの花がつき、甘い芳香が辺り一面に漂っています。たくさんの実が生りそうです!(^0^)
真夏日?
[令和1年5月10日]
令和初の真夏日だそうです。暑い!いきなりのこの暑さ、園庭や境内の木々が耐えらるか心配でなりません…。
園庭の鯉のぼりは青空に気持ちよく泳いでいます。でも今日でいよいよお別れです。今年は連休が長かったので少し早めに挙げましたが、お別れはやっぱり寂しいです…。
木陰では山砂が大活躍。
鍋にてんこ盛り!
この感触!
黙々と熱中しています。
こちらは何を見ているのかな?
ギョギョギョ〜! 羽アリ(シロアリの成虫)の大群です!
今日はこれが一気に飛び立つ日だったみたいです。園庭に置いてある数本の丸太から同じように大群が発生。子供達はすごい瞬間を目撃しました。本当にこの数が一気に飛び立つんです。フワフワフワ〜ッ!て。
シロアリは家の土台に入ると困りますが、実は自然の朽木には普通にたくさん住んでいます。園庭に転がしてある丸太も、こうやって毎年シロアリの大群が発生し飛び立っていきます。まるで保育園でシロアリを養殖しているみたいで嫌な感じもしますが、でも毎年これを見ると自然の神秘というか命の営みというかを感じます。フワフワと飛び立つシロアリの大群を見て、子供達はかなり興奮していました。
ゴールデンウィークが終わり、花が咲き、木々が芽吹き、子供達の自然あそびが充実する時期になりました。
花まつり
[平成31年4月14日]
4月8日はお釈迦さまの誕生日。この日を「花まつり」と言います。保育園では毎年子供達とお祝いをしています。
各家庭から持ち寄られたお花で飾った花御堂(はなみどう)。
真ん中に立つのは生まれたばかりお釈迦さまです。
マヤ夫人(お母さん)の右の脇からスポーンと生まれたお釈迦さまは、すぐにスクッと立ち上がって七歩歩き、天と地を指差して「天上天下唯我独尊!」と叫んだと言われています。
みんなでお釈迦さまのお祝いの歌を歌い、
園庭に出て白象を引っ張ります。
お釈迦さまをお母さんのお腹の中に運んでくれたと言われる、6本の牙を持つ白い象。その姿をしげしげと眺めていた男の子がポツリと言いました。
「牙が6本じゃないじゃないか…。」
あ、イタタタ…、鋭い意見。実は私も毎年思ってたんですよ、なんで牙が2本なんだ?6本で作ればよかったのに!と…。「あ、3本の牙が固まって1本に見えるんじゃない?」と、思わず苦し紛れの言い訳をしてしまったじゃないですか、もう!
子供はよく話を聞き、よく見、よく考えていますね。素晴らしいです。とにかくこの2本の牙のかわいい白象を引っ張って、みんなで本堂に参拝です。(^^)
テラス前にも花がたくさん。まさに花の季節です。
その後、一人一人お釈迦さまに甘茶をかけてお参りします。
「お釈迦さま、おめでとうございます!(^^)」
お釈迦さまがお生まれになった時、空に竜が現れて甘い雨(甘露、アムリタ)を降らせお釈迦さまの体を洗い流したと言われています。そして辺り一面にはきれいな花が一斉に咲いたそうです。天と地が仏の誕生を祝福したのですね。その伝説によって、4月8日にはたくさんの花を飾り、赤ちゃんの姿をした誕生仏に甘茶をかけてお祝いするようになりました。甘茶をかけることを灌仏(かんぶつ)と言います。仏をすすぐ、という意味です。甘茶はつまり竜の降らせた甘露の雨の代わりというわけです。
花まつりはお釈迦さまに甘茶をかけてお祝いし、同時に、この世にある一つ一つの命の尊さを噛みしめる日でもあります。この日は「いのちを祝う日」でもあるわけです。子ども達一人一人が、その命を精一杯輝かせて生き生きと歩いていけるように、私たちは共に歩き支えていきたいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日が変わって4月13日(土)、妙福寺の会館「本應院」で練馬区仏教会合同花まつり法要が行われました。
ゲストに練馬区在住の笛演奏家 一噌幸弘さんをお招きし記念コンサートを行いました。世界の様々なアーティストとコラボレーションを重ね、テレビなどでも活躍されている一流の能楽師・笛演奏家です。贅沢な4人編成、美しい笛の音色、テンポの良いリズム。聴いていると体が自然に動き出してしまいます。一噌さんの演奏はいつ聴いても素晴らしいです。本当に贅沢な時間でした。
こうして、いのちのお祝い週間は過ぎていったのでした。