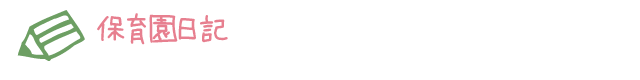らーめん屋
[平成29年2月16日]
ねはんえ
[平成29年2月15日]
2月15日は涅槃会(ねはんえ)でした。
涅槃会というのは、仏教のはじまりである「お釈迦さま」がお亡くなりになられた日。ご命日の記念日です。
幼児クラスが本堂に集まって涅槃会の歌をうたい、お話を聞きました。そして代表園児の声に合わせて良い子のお約束をしました。
一人一人心を込めてお焼香をします。
最後に大きな涅槃図(お亡くなりの絵)を見て、園に戻りました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご承知のように、仏教はお釈迦さまによって始まりました。お釈迦さまは私たちと同じ人間です。インドで生まれ、修行をしてさとりを開かれ、人の「生き方」を説かれたのです。そして80歳で亡くなられました。
お釈迦さまの説いた「生き方」の教えが、多くの人々の心に染みわたり、語り継がれ、まとめられ、やがてお経というものになって日本にもたらされました。
この世の成り立ち、人の心の動き方、物事の繋がりなど、すべてを一瞬にしてクリアに見通す力をお釈迦さまは獲得されたのだと思います。それが「さとり」です。そしてその境地から振り返って現実の私たちの姿を見て、どのような心持ちで過ごせば安らかで幸せに生きることができるのかを説かれたのです。仏教が「哲学」と呼ばれる所以です。
「人が死ぬ」ということについて、子供たちに静かに語り考えることができるのは素晴らしいことです。誰でもいつか必ず死んで別れなければなりません。その悲しみや寂しさをじっとかみしめることで、逆に今ここに共にあることの嬉しさや大切さをかみしめることができるのではないでしょうか。
人に優しく、きまりをよく守り、がまん強くやり遂げ、丈夫な体を作り、いつも心を落ち着かせ、物事をよく考えて良いことをする。それがお釈迦さまの説かれた教えです。お釈迦さまは2500年前に亡くなられましたが、その教えは今でもここに生き続け、私たちの心を明るく照らしてくれる灯火となっています。私たちは皆、仏の光に包まれているのです。
涅槃会は、お釈迦さまの死と向き合い、生きることを見つめ直す日です。子供達とそんな気持ちを少しでも共にできる時間を過ごしたいと思います。
ウッドデッキのメンテ
[平成29年2月11日]
建国記念日です。園児のいない祝日に、集まれる職員でテラスのウッドデッキのメンテナンスを行いました!
なんだかちょっと怪しい光景…?笑)まず隙間に入り込んだ砂をきれいに掃き出し、その後に浸透性オイルを塗布していきます。
年長の保護者が、親子連れで手伝いに来てくださいました。(5組)
前日に急遽お声掛けしたにも関わらず、ありがとうございます!
パパ達の心意気に超感激!
なぜか卒園児の親子も飛び入り参加! センキュー!(^^)
だいぶ良い感じになって、
きれいに仕上がりました!
バンザーイ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このウッドデッキの材はウェスタンレッドシダーです。柔らかくて温かみのある材質と美しい色合いが個人的に好みです。セランガンバツーなどのハードウッドとどちらにするか散々迷いましたが、やはりこちらにしました。加工しやすい木なので施工業者は大喜びしてました。笑)
保育園のテラスという場所は、デッキ材にとってそれなりに過酷だと思います。デッキ表面はとにかく砂埃で常にザラザラ。晴れの日は強い陽射しが射し込みますし、雨が降れば吹き込みと跳ね上げでなんだかんだビショビショになります。そこを毎日毎日170名規模の人間が朝から晩まで行ったり来たりするのです。屋根下ですので湿気で腐る心配は少ないかもしれませんが、湿気以外の面で条件は過酷だと思います。なので、このレッドシダーのデッキは私にとっての一つの実験です。どんな感じかな〜と。
完成当初(平成26年夏)は木の色合いが美しく、あたたかで素敵な雰囲気。
約2年半、ノー・メンテ。色味はかなりシルバーグレーに。しかも表面はヤスリ掛けしたようにガサガサです。砂埃が乗った状態で上履きで歩き回るからですね。
無垢材の良いところは古びてもそれが味になるところでしょう。メンテナンスを怠らなければ、経年変化とともに傷や削れが子供達の歴史を物語るようになります。2年半ノーメンテはちょっとサボり過ぎました。今後は最低でも年に1度はオイルを塗布してメンテナンスしてきたいと思います。
自分達の居場所を自分達で手入れするというのはとても大事なことです。愛着が湧き、大切に扱う気持ちが芽生えます。まずは職員ですね。自分達の生活を支えてくれる大切な職場ですから。そして子供達。自分達の園です。そして、お父さんお母さん達もです。自分の子供が1日の大半を過ごす大切な場所です。園に関わる人達が互いに力を出し合って、愛情を込めて居場所を大切にしていかないといけません。
ちなみに使用しているオイルはワトコのティンバーガードです。自然にも人体にもなるべく優しい(と思われる)塗料を選んでいます。リボス、オスモなど色々迷いますが、半屋外のこのテラスは今のところこのオイルに落ち着いています。
今日は本当にお疲れさまでした!お手伝いしてくださったお父さんお母さん方、そして子供達、ありがとうございました!(^o^)/
投げる
[平成29年2月8日]
年長のドッヂボールが盛り上がっているせいか、近頃園内全体でボール遊びが盛んです。そこで、「投げる」ということと運動発達について少し書きたいと思います。
「投げる」という動作は、実は幼児期の子どもにとってかなり複雑で高度な動きであると言われています。
小さな子供が初めてボールを投げる時、ボールを手で前に押し出すような形で投げることがほとんどです。やがてそこにテイクバックや体軸の回旋、足の踏み出し、体重移動などが加わっていきます。そして最後は手を大きく振りかぶって体を弓なりに反らせ、ボールに体重を乗せて投げるという動きができるようになっていきます。
一つ一つの個別の動作を確実に習得し、脳が指令を出してそれらを総動員しながら、体を絶妙にコントロールしてはじめて「投げる」という動作が完成するのです。だからボールを投げる姿が、その子の運動発達のバロメーターの一つのように扱われることもあります。
足を上げての体重移動も、小さい子にとってはかなり高度な動きです。
年長男子のフォームは、さすが。
保育界・教育界では、随分前から子供の運動能力の低下に対し警鐘が鳴らされています。最近の子供は自分の体を上手にコントロールできない子が多いのです。小さな動作で言えば「靴紐が結べない」とか、咄嗟のことで言えば「転んでも手が出ない」とか、遊びの中で言えば「リズムに合わせてうまく体を止めたり動かしたりできない」とか。身体を操作する能力が低下してきているのです。実は運動能力の発達は、意欲や気力などの精神面の発達にも繋がっていて、運動能力が低下すると物事に対する意欲ややる気も低下していくと言われています。運動能力は、子どもが「生きる力」を身に付ける上でとても重要な要素の一つなのです。
ドッヂボールは、園庭で子供が多くの運動能力を獲得できる遊びの一つだと言えると思います。
ただ…、平らな園庭というのもまた、ある意味問題なわけです。
例えば「走る」という動作を見た場合、平らなグラウンドだけでは使う動作は限定的です。そこに斜面や段差が加わると途端に足元が不安定になり、要求される動作が格段に増えます。不安定な危ない足元の状況が、子供の運動発達を促し、身体コントロール能力を高め、それが精神面や情緒面の発達にも良い影響をもたらしていきます。
太鼓橋で戯れる子猿たち。(^^) 上半身の運動能力も大切。
カーニ♪ カーニ♪ と、リズムをとりながら横歩き。2歳の発達に大切な要素。
お、順番待ちもしっかり並べていますよ。
蹴るのも大事。
運動発達が順調だと、コミュニケーション能力も順調に育ちます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
妙福寺の園庭は広いのですが、ほぼ真っ平らなので今ひとつイケてません…。ここで子供が習得できる動作は種類が少ないという意味です。広い園庭というのはそれだけで贅沢ではありますが、他の園ではたとえもっと狭くても子供の発達に最高の園庭作りをしているところがあります。私は最終的には園庭全体を森と山にしたと思っているのですが、まあそれにはもう少し時間をください。
ただ、うちの園には林(第二園庭)があります。そこがうちのめっちゃ贅沢なとこなわけです!(^0^)
と、とりとめがなくなってしまいましたが、これが乳幼児期の重要な「教育」の一つだということを言っておきたいと思います。保育園はただ遊んでいるのではありません。遊びが子供の成長発達にとって非常に重要であり、その遊びの「質」が、その子の人生の質を左右すると言っても良いと思います。だから保育園はその「遊び」を科学して、子供の豊かな成長発達を支援するのです。それが保育園の仕事であり教育なのです。
3歳クラスの子達が大好きな丸太の山。
彼は今、トイレットペーパーの芯を望遠鏡にして、何かの主人公になりきって探検をしています。(^^)
以前とある園の園長先生から「なんでこんな危ないものがあって平気なんですか?」と言われてしまいました。もちろん私達なりに考えて安全は確保しています。子供はこういう所を登ったり降りたりするのが大好きですし、それがまた子供の発達にとても必要なことだと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
年中の女の子と葉っぱで遊んでいたら、こんなのができました。
「バッタみたい!」
と喜んでくれました。
「バッタが飛ぶよ。ピョーンピョーン。ほら、これカバンにもなるんだよ。こうやって持つの。ここを開けるとお金を入れられるよ。お財布にもなるんだよ。」
子供の口から次々と発想が飛び出します。
自然のこと、運動発達のこと、だけじゃなく、とにかく色んなことを考えながらみんなで楽しく保育しています!