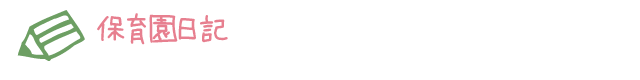泥んこ(番外編その2)
[平成27年5月18日]
最近の泥んこ&土いじり。本編を差し置いてまたまた番外編、その2!
本日登園して驚いた方も多いかもしれません。土曜の午後に花壇(畑)を作りました。
年中クラス前
年長クラス前
素晴らしい出来!(自画自賛) 枠組みに使ったのは園庭や境内の木で、剪定後捨てずにとっておいた丸太です。年中の方はイチョウ、ケヤキ、サクラ。年長の方はイヌシデとコウバイ(紅梅)。色んな木が混在してます。防腐処理など一切していませんので、やがて朽ちてボロボロになってしまいますが、恐らく数年は持つでしょう。最後は土になって土壌を豊かにしてくれるってのが最高に素敵ですし、安心です。
寺の貯木場?(笑)から適当な太さの丸太を選別し、リヤカーに積んで園庭に搬入。姿形を見て色々組み替えながらチェーンソーで長さを整え、カスガイで固定します。これで枠組みは完成。
次に枠内の土を掘ります。グラウンドの表面はカチカチのダスト。ツルハシで10センチほど掘り起こすと土が見えてきます。スコップでダストを取り除き、その上から園芸用土を投入します。土の配合はお寺の檀家さん(元園芸店主)が指導してくれました。腐葉土や牛糞などを混ぜて撹拌します。
さて、植えるものをまだ決めていなかったのですが、「だったらうちに苗がいっぱいあるから持って来てやるよ。」と檀家さんの一声。「え、ホントですか?!超嬉しい♪」と言うことで、フットワーク軽く軽トラで新座の自宅まで取りに行って下さり、約40分後、ナスやピーマンの苗を持って戻って来てくれました。
この作業をしていたのが午後3時頃だったので、ちょうど午後の外遊びに出てきた子ども達に手伝ってもらい、土に穴を掘ってポットの苗を畑に植え替えていきました。
そして完成。素晴らしい畑。虫除けにマリーゴールドも一緒に植えました。きれいです。楽しみ。結局、土も苗も全て檀家さんが寄付してくれました。本当に有り難いです。なので今回の制作費は0円。いや、カスガイを購入したので正確には800円くらいかな? いずれにしても素晴らしい! 更に何ヶ所か作っちゃうかも知れません!
子ども達にしっかり世話をしてもらい、皆で美味しい野菜を収穫したいと思います!
泥んこ(番外編)
[平成27年5月15日]
同じ泥んこではありますが、番外編です。



下準備ほぼ完了。もうすぐ田植えです。意味がよくお分かりにならない方はこちらをご覧ください!
さて、今年は昨年の反省を踏まえ、ある秘策を考えています。果たして上手くいくのでしょうか…。乞うご期待!(また?)
シロツメクサ達、今年も元気です。
泥んこ
[平成27年5月14日]
さて、昨日の報告の続きです。今回は林で思いっきり泥んこ遊び。
園庭の土と林の土って違うのかな? 実験を兼ね、何日もかけて子ども達と一緒に穴を堀り、根っこや石を取り除き土を耕します。園庭の砂混じりの土と違い、黒くて柔らかい土です。手押し車やバケツ、シャベル、タライなどを林に持ち込んで遊びの環境を整えていきます。準備の一つ一つがどれもみんな楽しい泥んこ遊びのプロローグです。
林の音を聞き、土の匂いを嗅いでみます。ある男の子が叫びました。
「あ、カブトムシの土の匂いがする!」
そう、彼は日頃お部屋で世話しているカブトムシの土の匂いを覚えていたのです。実はお店でよく売られているカブトムシの土はクヌギの腐葉土。そしてこの林の土もクヌギやコナラの枯れ葉で覆われています。つまり彼の嗅覚は素晴らしく正確だったわけです。

穴に水をそそいで土をこね、
タプタブの感覚を楽しみます。
お、泥あそびの定番「泥だんご」。

団子をひたすら磨く少年。
担任の柔らかいお尻で磨く! ナイロンの生地感とお尻の弾力が、磨きに最高です。

やがて、カチカチのツルピカになっていきます。
そして、できた団子をどんぐりコロコロの竹筒に転がして遊んだりもしちゃいます!転がってきた団子を慌ててキャッチしたり、飛んで地面に落ちても割れないことに感動したり…。

もう、嬉しくって草むらを駆け回ります。笑
……続く
台風一過
[平成27年5月13日]
季節はずれの台風一過の林
さて、一体何をしているのでしょう…?
ほうほう、
ん?
乞うご期待!